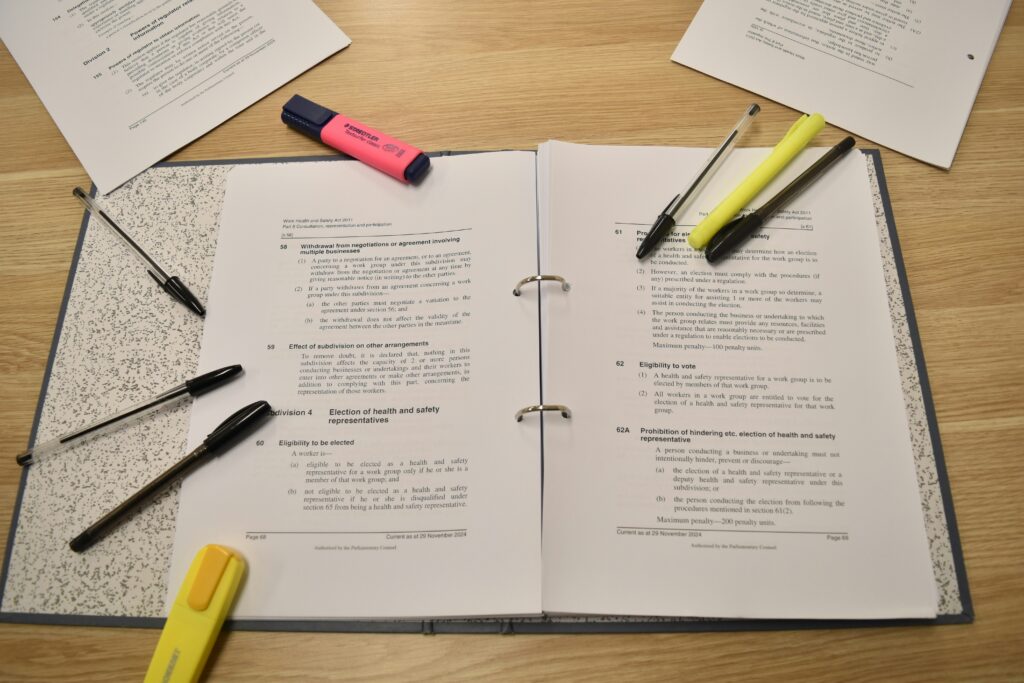
夏休みの宿題で多くの小中学生を悩ませているもの、それは「自由研究」ですよね。
前回の記事では、「簡単だけどそれっぽく見せれる研究」を紹介しましたが、今回の記事では、「入賞できる作品にするためのコツ」を、元審査員の視点から解説していきます。
どんな研究でも、工夫次第で作品の質は飛躍的に上昇します。
みなさんも自分の作品をぜひ見直してみてくださいね!
それでは、いってみましょー!
「自由研究」ってなんだろう?
そもそも自由研究はなぜ宿題になっているのでしょう。
「宿題」とは皆さんに力を身につけてほしいから出されるものです。
では、どんな力を身に着けてほしいかというと…
「なぜ?」「どうして?」という疑問を、自分で解決する力です。
裏を返せば、自由研究を一生懸命やれば確実にこの力が身についていくということです。
教師を辞めてなお思いますが、この力は社会で非常に役に立ちますし、大切です。
なぜこの問題が起きるのか、原因は何なのか、どう解決していけばいいのか、具体策は…。
挙げればきりがないですが、確実に自分自身を成長させますし、周りからも重宝されます。
みなさんもぜひ、自分自身を成長させてくださいね。
ポイント① 「研究の流れ」がしっかりしていること

夏休みの自由研究に限らず、世界で活躍してる多くの研究者も「研究の流れ」は必ず意識します。
その流れは、
テーマを決め、仮説を立て、実験や観察を行い、結果を分析し、自分なりの考察をまとめる
ということです。
逆にいくらテーマや仮説が面白くても、実験をがんばっても、この流れができていないと入賞はできません。
みなさんの作品はどうでしょうか。
この流れができている大前提のもと、プラスアルファで入賞のコツを紹介していきます。
ポイント② 小中学生らしい親密感のあるテーマであること

私が小学生の時、「DNAの秘密をさぐる」といった内容の研究を行ってきた子がいました。
「こんな難しい研究だったら、絶対この子は入賞するだろうなぁ…」と思っていましたが、その研究が入賞することはありませんでした。
審査員からすると、「この作品は本当にこの子の研究なのか?」という疑問が浮かびます。
実際に私が審査員をしていた時も、この作品は明らかに親の作品だなというのがまるわかりの物もありました。
もちろん、その作品がどのような経緯でつくられたかは審査員には分からないので、冒頭で書いた「研究の流れ」がしっかりしていて、研究として成り立っていれば入賞もあり得ると思います。
親の手を借りるな、とは言いませんが、審査員は「その子らしさ」と「視点のおもしろさ」「その子のがんばり」などが見える作品に惹かれるものです。
もしこの記事を読んでいる保護者の方がいたら、ぜひ、「その子の成長」につながる手助けをしてあげてください。
「どうしたらうまくいくかな?」や、「こんな実験をしてみたらいい研究になるんじゃない?」とか、考えるきっかけを作ってあげましょう。
全部を親がやるのではなく、伴走しながら一緒に作品を作ってあげてください。
研究の例として、ある年に夏の車の中でゆで卵をつくる実験をしている研究がありました。
字も汚く、まとめもぐちゃぐちゃで入賞こそできなかったものの、ユーモアあふれる文章と好奇心マックスで行われていたその研究に、「特別賞があったなら、間違いなくこの子だったね」と審査員からは大好評でした。
無理に難しい研究をする必要はないので、純粋な好奇心を、おもいのまま作品にしてみてください。
ポイント③ 研究のきっかけや仮説が、具体的で明確であること

例えば、前回の記事でも紹介した「ろ過実験」のきっかけを考えてみましょう。
ネットで見ておもしろそうだから、やってみようと思った。
これではさすがに不十分ですね。
前回の記事では、以下のような文章を書きました。
日本は地震や集中豪雨などの自然災害が多く、今後水道が使えなくなることもあるかもしれない。また、SDGsの目標6には「安全な水とトイレを世界中に」という目標が掲げられ、安全な水の確保は世界的に見ても重要な課題と言える。そこで今回の研究では、身近なものでろ過装置をつくり、実際にきれいな水をつくることができるか、実験してみた。
このままでも十分ですが、ここに具体性を足していきます。
例えば、具体的な数字を入れてみるとこんな感じになるでしょうか。
1日に必要な水分量(ml)は、体重(kg)×30~40(ml) という式で表される。
自分の体重が〇kgなので、この研究では□mlのきれいな水をつくってみることにした。
このように、やり方や考え方次第でいくらでも具体的に設定することができます。
具体的に目標を設定するメリットは、「ゴールが明確になる」ことです。
例えば、「きれいな水をつくる」より、「きれいな水を□mlつくる」の方がより達成するべき目標がはっきりしますよね。
自分の研究はどこをゴールにするべきか、考えてみてください。
ポイント④ データや実験、文章量が豊富であること

自由研究では「質」も評価されますが、何より「努力量」が重要になります。
「この子はがんばって毎日観察を行っているなぁ」とか「実験データがこんなにもあるのか!」とか、審査員はあなたの努力を評価してくれます。
手間はかかりますが、研究の質を上げる大切な要素ですので、具体的な方法を紹介します。
データは平均をとる
例えば、ペットボトルロケットを飛ばす実験をしたとしましょう。
1回飛ばして終わりでは、果たしてそれが本当に正しい結果なのかが検証できません。
もしかしたら偶然機材が不具合を起こしているかもしれないし、風の影響を受けているかもしれません。
何回もデータをとり、極端におかしな値は外したうえで平均をとると、信頼のある数字になるでしょう。
極端な値が出た場合、理由を考察してみるとさらに深みのある研究になりますね。
失敗もデータとして残す
科学者の研究は「成果」が大事ですが、皆さんが行っているのは「夏休みの自由研究」です。
失敗もぜんぜん問題ないです!
むしろ、考察して再実験して…とやっているうちにどんどんデータがたまっていきます。
エジソンも電球を発明するのに10000回失敗したといわれています。
このことに対してエジソンは「これは失敗ではない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ。」という名言を残しています。
「失敗はおいしいネタ」とでもとらえておきましょう。
実験の種類を増やす
研究では、自分の仮説や予想が正しいことを第三者に正しく伝えることが重要です。
実験結果が正しいことを証明する証拠は、多いに越したことはありません。
「この方法でうまくいったなら、この方法でもうまくいくはず」など、あらゆる角度から実験してみましょう。
特に、対照実験は研究の基本中の基本です。
対照実験の解説や取り入れ方については、前回の記事をご覧ください。
ポイント⑤ 実験データから深い考察がなされていること

実験をやったはいいものの、そのデータをうまく使えなければ意味がありません。
まずは、グラフや表にまとめて、見やすく整えましょう。
そこからわかることを深堀りしていきます。
「グラフから、〇〇ということがわかります」のように、データが示している事実を具体的に書き出したり、実験前に立てた仮説と、得られたデータを比較し、「仮説通りだったのか」「なぜ違ったのか」を考え、その理由を考察します。
また、データから見えてきた傾向や結果について、「なぜそうなるのか?」と問いを立てて、その原因や背景を考察しましょう。
例えば、「〇〇の条件で結果が大きく変わったのは、△△という原因が考えられる」といったように、自分の言葉で説明してみましょう。
考察はあなたの研究の集大成です。
実験データを存分に活用してください!
ポイント⑥ レイアウトが整っていること

上でも解説していますが「あなたの研究を、見ている人に正しく伝える」ことはとても大切です。
せっかくよい研究を行っても、それが伝わらなかったら悲しいですよね。
例えば、「色を工夫する」だったり、「字はていねいに書く」、「見やすいグラフや表をつくる」など、工夫できることはたくさんあります。
ただし、「絶対にパソコンを使って、きっちりとまとめろ」とか、「字は教科書のようにきれいに書け」と言っているわけではありません。
わかりやすくなるならパソコンを使ってもいいし、きれいに書けるなら字はきれいに書くべきですが、大切なのは「どうしたら読みやすいかな」「どうしたら伝わるかな」と相手のことを考えることです。
審査員はそういった努力もちゃんと見ています。自分なりのまとめ方をしてみてください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
いろいろ書きましたが、みなさんにはなにより「研究を楽しむこと」を忘れないでほしいです。
失敗しても一歩一歩成功に近づいていく感覚や、実験が成功した時の感覚、そして普段できないことにチャレンジすることは、きっとみなさんを成長させてくれるはずです。
みなさんの研究が少しでも良いものになるよう、力になれたらうれしいです!
それでは、また!がんばってくださいねー!




コメント